企業総合保険の上手な活用術
まだ軌道に乗っていない会社であれば保険料の安さ重視でいいですが、利益が出ていて従業員も多い事業であれば地震や火災など幅広いリスクでも乗り切れるような内容で火災保険(企業総合保険)に入らないといけません。
事務所・工場は火災保険単体加入はしない?
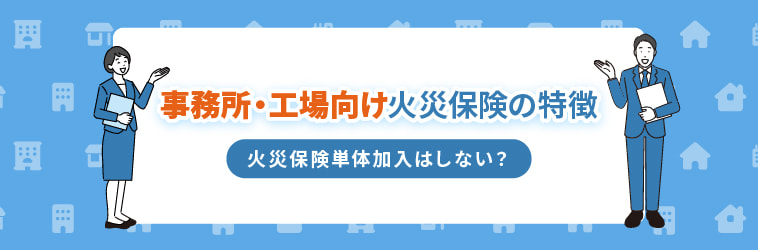
事務所、工場、オフィスなどは火災保険の単体加入はせずに「企業総合保険」で加入するのが一般的です。大手損保会社は「店舗・オフィス用火災保険」として案内をしています。
住宅向け火災保険と同様に基本補償や地震保険の有無を選択する点までは通常の火災保険と共通です。企業総合保険は、建物の火災や天災、トラブルによる損害だけではなく事業を運営するにあたって起こりうる、さまざまなリスクを補償する保険をセットにできます。
また、複数の事業所を持っている場合は1つの保険契約に全ての事業所の火災保険をまとめることも可能です。複数の保険契約を持っている場合は、1つにまとめるだけで保険料を安くできる場合もあります。
休業損害補償と利益保険が重要
事務所や工場の火災保険は、建物や設備、財産の修復・現状回帰だけではなく、仕事を稼働できなくなった部分の休業補償を考えないといけません。
たとえば従業員のいない個人事業主で自宅の一部をオフィスに使っていて、万一の際は数ヶ月生活できる余力があれば、一般的な火災保険と同じ内容で構いません。
しかし、高額なテナント料や事業ローンを組んでいる工場や事務所が火災で稼働できなくなると、家賃や借金の支払いの問題をはじめ、従業員の給料補償など出て行く支払いは多数あります。事業によっては注文を受けていた仕事がキャンセルになって仕入れ費用や外注費の損失が出ることもあります。
ささいな不始末から火災が発生して、大きな利益を出していた会社が倒産するケースはよくあります。店舗・オフィス用の企業総合保険ではリスクを幅広く補償できます。
しかし、補償範囲が広くなれば当然保険料も高額になります。代理店との付き合いや紹介などで比較せずに保険会社を選んでいる会社も多いですが、単価の大きい事務所・工場向けの火災保険は、保険会社や補償内容を見直すと年間数十万円~数百万円も保険料を節約出来る場合もあります。
地震保険も事務所・工場は専用プランの用意がある
住宅用地震保険は損保会社と政府(国)の共同保険になっていて、基本プランでは建物価格の50%までしか補償されません。住居であれば震災時に仮設住宅の用意や、親戚などからのカンパなど、全額補償されなくても最低限の生活を続けることができます。
しかし、事務所や工場の事業用物件は地震で稼働できない状態に陥ると50%の補償では事業の存続ができなくなってしまいます。
企業総合保険向けの地震保険は補償内容を細かく設定できて、主に次の2種類のタイプを用意されています。
限度額と控除額を設定して保険料を支払う方式。
たとえば建物価格1億円で限度額7,000万円、控除額1,000万円の契約の場合、8,000万円以上の損害で控除額を差し引いた上限の7,000万円の保険金が出ます。
8,000万円未満の損害の場合、実損額から控除額1,000万円を差し引いた金額を補償されます。
(例)
- 7,000万円の損害→6,000万円の保険金
- 3,000万円の損害→2,000万円の保険金
- 1,000万円以下の損害→保険金なし
縮小支払方式
損害額から事前に設定した控除額を差し引いた額に対して、縮小割合を掛けて保険料を算出します。
たとえば、建物の保険価格1億円で控除額30万円、縮小率70%の場合、損額額(上限1億)から30万円を引いた70%が保険金になります。
(例)
- 1億円の損害→9,970万円×70% = 6,979万円
- 5,000万円の損害→4,970万円×70% = 3,479万円
日本は地震大国で、利益の出ているビジネスを大震災で全て失ってしまうリスクは背負いたくないものです。
100%の補償は難しいですが、キャッシュフローなども考慮して、どのくらいの自己負担金で窮地を乗り切れるのか計算して根拠のある補償内容で地震保険に加入しましょう。
まとめ
事務所(オフィス)・工場の火災保険は企業総合保険で加入する流れになります。扱っているのは大手代理店型損保会社になります。保険料も重要ですが、企業の存続が困難になる状態を回避する内容で保険に加入しないといけません。
まだ軌道に乗っていない事業であれば、最初は最低限の内容にして会社が成長したら保険内容も見直して手厚くしましょう。
適切な保険プランを選ぶには専門知識が必要です。また保険料率も保険会社ごとに違うので保険会社を変えるだけで補償を手厚くして保険料を安くできる場合もあります。
複数社から話を聞いて保険料と信頼できそうな保険募集人のいる所で加入しましょう。



